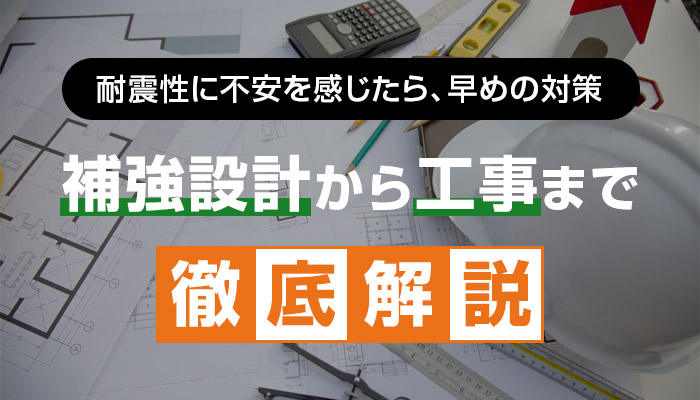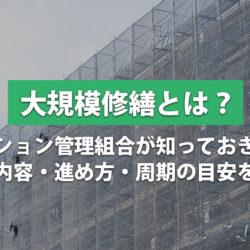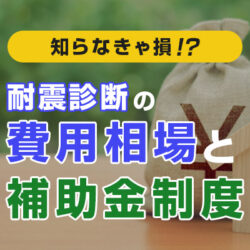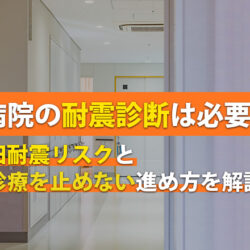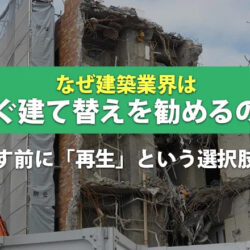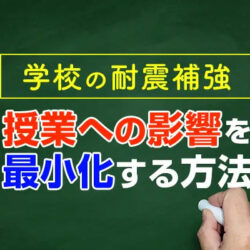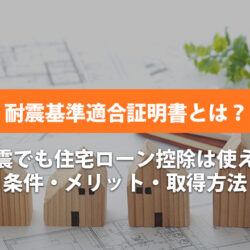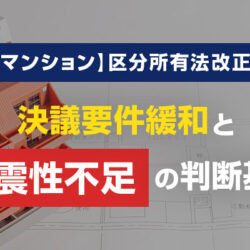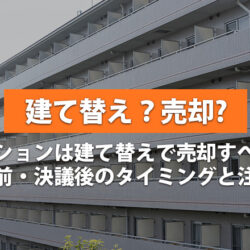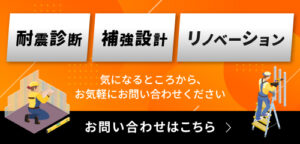大地震から命と財産を守るためには、まず建物の耐震性能を知ることが何よりも重要です。 もし耐震性に不安を感じたら、早めの対策が欠かせません。 補強の計画や方法は建物の用途や構造、法的基準によって異なります。 その判断基準や工事の流れを本文で詳しく解説します。
耐震補強の概要と計画の流れ
耐震診断の結果、耐震性が不足していると判定された場合でも、適切な耐震補強を施すことで、現行の耐震基準で建てられた建物と同等の耐震性能を確保し、法的には「耐震基準に適合」した建物とすることが可能です。
耐震診断で補強が必要と判断された場合は、まず耐震補強計画(耐震補強案と概算補強工事費の算定)を行い、その後、耐震補強を実施するのか、建て替えるのかを決定します。 耐震補強を選択した場合は、目標とする耐震性能を満たすために耐震補強設計(詳細設計)を行い、その設計図面により、工事見積、工事業者選定、工事契約、工事着工と進みます。
<参考>既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会「耐震判定委員会」
https://www.kenchiku-bosai.or.jp/assoc/nw/hantei/
耐震診断や耐震補強計画の妥当性を第三者が技術評価する制度で、全国で広く活用されています。公共建築物や、民間建築物への補助金交付決定の際には「耐震判定委員会」による判定書が必要条件となることが多いです。
耐震補強の目的と種類
耐震補強とは、建物の壁、柱、梁などの耐力・剛性・靭性(ねばり強さ)を向上させ、地震時の損傷を最小限に抑えるための改修工事です。 診断結果に基づき、建物の剛性・耐力のバランスを確保したうえで、使用性や施工性、工期、コスト、デザインなどを総合的に考慮します。 また、構造特性や施工可能な箇所の制約に応じて、複数の工法を組み合わせることも一般的です。
耐震補強は、大きく以下の3つの技術に分類されます。
- 耐震:建物の粘りや強度を高め、大地震時でも倒壊を防ぎ人命を守る
- 制震:地震エネルギーを吸収し、揺れを軽減する
- 免震:地盤からの揺れを直接建物に伝えない
多くの補強工事は「耐震」が中心ですが、病院や避難所など、より高い安全性を求める場合は制震や免震を組み合わせる場合もあります。
耐震補強の目標値とIs値(構造耐震指標値)
耐震補強を行う際は、建物用途に応じた目標性能を設定します。
・一般建物
中規模地震(震度5強程度)に対しては、損傷が生じる恐れは少なく、大規模地震(震度6強から7に達する程度)に対しては、損傷は許容するが倒壊・崩壊する危険性を低くし人命を保護を目的とする。
必要最小となる構造耐震指標値(Is値=0.60)を目標値とする。
・避難施設・病院・防災拠点など
大規模地震(震度6強から7に達する程度)後も、建物機能を維持するため、必要最小となる構造耐震指標値(Is値=0.6)の1.25〜1.5倍程度(Is=0.75〜0.90)を目標値とすることが多い。
耐震改修促進法に基づく、耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価
| 耐震診断の方法 | 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価 | |||
|---|---|---|---|---|
| 安全性評価Ⅰ | 安全性評価Ⅱ | 安全性評価Ⅲ | ||
| 地震の震動及び衝撃に対して 倒壊し、又は崩壊する 危険性が高い。 |
地震の震動及び衝撃に対して 倒壊し、又は崩壊する 危険性がある。 |
地震の震動及び衝撃に対して 倒壊し、又は崩壊する 危険性が低い。 |
||
|
鉄骨造(S造) 一般財団法人日本建築防災協会による 「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版、2025年版) |
Is < 0.3 または q < 0.5 |
左右以外の場合 |
0.6 ≦ Is かつ 1.0 ≦ q |
|
|
鉄筋コンクリート造(RC造) 一般財団法人日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める 「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版、2017年版) |
Is/Iso < 0.5 または CTU・SD < 0.15・Z |
左右以外の場合 |
Is/Iso ≦ 1.0 かつ 0.3・Z ≦ CTU・SD |
|
|
鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) 一般財団法人日本建築防災協会による 「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める 「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版) |
鉄骨が充腹材の場合 |
Is/Iso < 0.5 または CTU・SD < 0.125・Z・Rt |
左右以外の場合 |
Is/Iso ≦ 1.0 かつ 0.25・Z・Rt ≦ CTU・SD |
| 鉄骨が非充腹材の場合 |
Is/Iso < 0.5 または CTU・SD < 0.14・Z・Rt |
左右以外の場合 |
Is/Iso ≦ 1.0 かつ 0.28・Z・Rt ≦ CTU・SD |
|
Is:構造耐震指標
CTU・SD:累積強度指標と形状指標の積
q:保有水平耐力に係わる指標
Z:地域係数
Rt:振動特性係数
地震後の事業継続(BCP)や、補修による継続利用の観点はもちろん、構造体だけでなく、電気・空調・衛生設備や仕上げ材などの損傷を減らすためにも、補強目標Is=0.6では十分ではありません。
耐震改修促進法では、建物の耐震性能を測る指標としてIs値(構造耐震指標)が使われ、Is値0.6以上を「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。」としています。
・Is値0.6未満:耐震基準に適合していないため、耐震補強が必要
・Is値0.6以上:耐震基準に適合しているため、倒壊の危険性が低い
※ただし、損傷することを許容しており、継続利用の保証はしていない
補強目標Is値を高く設定するほど地震被害は減少しますが、補強量の増加に伴い建物の使用性や機能に制約が生じ、また工事費も増加します。 そのため、安全性、機能性、経済性、デザイン性のバランスを考慮し、耐震補強内容を計画することが大切です。
<参考>国土交通省「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001470933.pdf
既存不適格建築物の扱い
既存不適格建築物とは、建築当時は適法だったが、その後の法改正により現行基準に適合しなくなった建物を指します。 建築基準法上、原則として着工時の基準に適合していれば継続使用は可能ですが、防火・避難・耐震性能などが現行基準に満たない場合もあります。
耐震補強は単独で行うケースは少なく、増築や大規模改修と同時に行うことが多いです。 この場合、電気・空調・衛生設備の更新や内装改修も同時に行うことで、建物の安全性を高めると同時に、建物全体の価値も大きく向上させられます。
増築・大規模改修・用途変更等で確認申請を伴う場合には、既存不適格部分がある場合には現行の最新建築基準法に適合させる必要があります。
既存不適格部分の是正内容は、確認申請内容によって異なり、一部から全部是正が必要となる場合もあります。
「既存不適格の緩和条件」の適用により一部規定が除外される場合があります。 ただし、緩和措置は違反している規定については適用されません。
さらに「全体計画認定」(建築基準法第86条の8)では、既存不適格建築物(注意)を複数の工事に分けて段階的に改正後の建築基準法に適合させていく計画について、特定行政庁が認定を行うものです。
既存不適格建築物を一度に現行基準に適合させるのが難しい場合でも、全体計画認定を受けることで工事を複数の段階に分けて行うことができます。 増改築や大規模修繕だけでなく、用途変更などでも現行基準に適合させるための工事を段階的に行えるようになります。
「耐震改修促進法」の「認定」制度を利用すると、「大規模改修」の際に必要な「確認申請」が免除され、「耐震」以外の規定は「既存不適格」のままで可となる特例が受けられます。 また、低利融資、補助金の交付など、各種の優遇措置を受けることができる場合があります。
<参考>国土交通省「全体計画認定を活用した既存不適格建築物の増築等について」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zentaikeikaku.html
<参考>東京都耐震ポータルサイト「耐震改修計画の認定」
https://www.taishin.metro.tokyo.lg.jp/tokyo/topic11.html
まとめ
耐震診断の結果、耐震性が不足していても、適切な補強設計と施工によって「耐震基準に適合」した建物とすることは可能です。
補強の目標性能は建物の用途や利用目的によって異なり、Is値や機能性とのバランスを踏まえた計画が必要です。 また、既存不適格建築物の場合は法的制約や制限緩和措置を理解し、増改築や設備更新と併せて耐震補強を行うことで、建物の価値と安全性を同時に高められます。
特に昭和56年以前に建てられた建物は「旧耐震基準」建物となりますので、耐震診断による耐震性の検討が必要です。
大地震から命と財産を守るために、まずは現状の耐震性能を把握することから始めてみませんか?
リボビルでは、耐震診断から補強設計、工事まで一貫してサポートしています。 お持ちの建物が安全かどうか気になる方、補助金や工事費用の目安を知りたい方は、今すぐお気軽にご相談ください。
耐震診断・耐震補強設計(非木造)なら全国対応可能!
まずはお気軽にご相談ください。