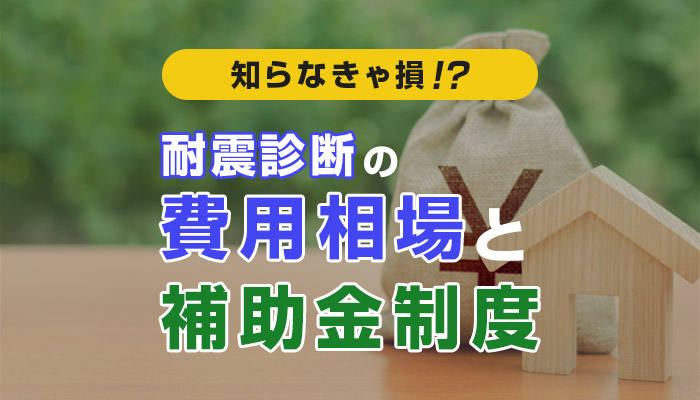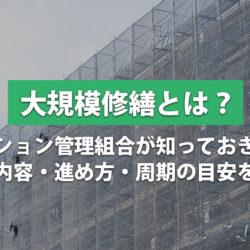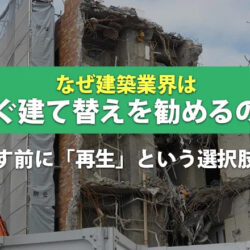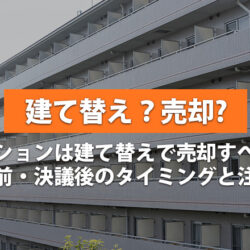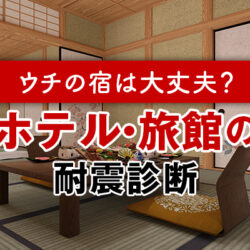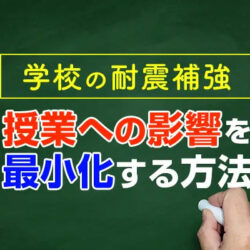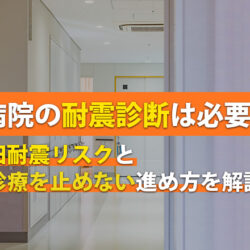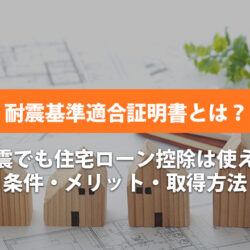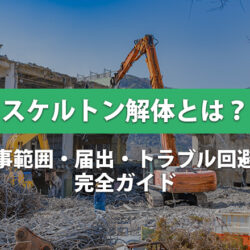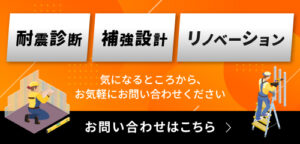1981年以前に建てられた旧耐震基準の建物は、大地震に耐えられるか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。 建物の安全性を確認する耐震診断は、命と資産を守る上で欠かせない備えです。 しかし、診断費用は建物の構造や規模によって数十万円から数千万円と幅広く、一歩踏み出せない方もいらっしゃるかもしれません。
そこでぜひ知っていただきたいのが、国や自治体の補助金・助成金制度です。 診断費用だけでなく、耐震補強工事まで補助金が利用できる場合もあり、経済的な負担は大きく軽減できます。 ただし、補助金・助成金制度の利用には「診断を始める前の事前申請が必須」といった重要な注意点があります。 この記事では、専門家としての見解を交えながら、耐震診断にかかる費用相場と補助金・助成金制度の賢い活用法を解説します。
耐震診断が必要とされる背景
建物を建築する際に遵守すべき建築基準法は、大きな地震が発生するたびに繰り返し見直されてきました。 とりわけ、1981年の大幅な改正で「新耐震基準」が導入されたのは、1978年の宮城県沖地震(M7.4)が大きなきっかけとなっています。 旧基準の建物は、1995年の阪神・淡路大震災(M7.3)で多くの被害が集中したことからも、耐震性能に課題があることが広く認識されるようになりました。
私たち専門家の視点から見ると、耐震診断は、単に法律を守るためだけのものではありません。 旧耐震基準で建てられた建物(既存不適格建築物)が、現行の基準と比べてどれほどの耐震性を持っているかを客観的に評価し、具体的な対策を講じるための、まさに「第一歩」なのです。
耐震診断の費用相場は?
耐震診断の費用は、建物の構造種別、規模、診断方法、設計図書の有無といった多岐にわたる要素を総合的に評価し、算出されます。 一般的には「1㎡あたり数千円程度」が目安ですが、これはあくまで一般的なケースにおける概算です。 特殊形状、特殊構造、異種構造建物等の場合は、目安の金額を大きく上回ることも珍しくありません。 詳細な費用については、個別の状況を正確に把握した上でのお見積りが不可欠です。
建物の種類別の費用感(参考)
| 建物の種類 | 耐震診断費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 戸建て住宅 ※木造 |
約60万円~100万円 | ※延床面積が120㎡前後の在来軸組構法1棟あたり |
| マンション・ビル ※RC造(鉄筋コンクリート造) |
約2,000円/㎡~約3,500円/㎡ | ※延床面積が1,000㎡~3,000㎡の建物の場合 |
| マンション・ビル ※S造(鉄骨造) |
約2,500円/㎡~4,000円/㎡ | ※延床面積が1,000㎡~3,000㎡の建物の場合 |
※上記の金額は参考の目安です。図面や検査済証の有無、また現地調査の内容等によって、実際の費用は前後する場合があります。
設計図面の有無による差
構造図や平面図などの設計図書が揃っていれば調査は効率的に進められます。 しかし図面が無い場合には、現地実測や非破壊検査、場合によっては破壊検査を行って構造を復元する必要があり、費用は1.5倍から2倍以上に膨らむことがあります。
診断方法の違い
診断には主に3つの方法があります。
-
第1次診断法(1次診断)
壁の多い建物に適した診断法となる。ただし偏心が過大な建物は2次診断を行う必要がある。 -
第2次診断法(2次診断)
学校校舎、事務所ビル、病院、庁舎等の建物で用いられており、最も診断実績の多い診断法で過去の地震被害における検証も多い。自治体による耐震診断助成金条件でも2次診断となっていることが多い。 -
第3次診断法(3次診断)
劇場・ホール等の大空間、ペンシルビル、14階程度までの高層ビル、特殊形状の建物等で用いられている。3次診断結果は2次診断結果より小さなIs値が算定される傾向が多く、地震被害状況との検証では耐震性能が過小評価される場合が多い。そのため3次診断の採用は、建物形状等により、2次診断だけでは耐震性の検討が難しい場合に併用して行うとしていることが多い。
特に劇場・ホール等の大空間、14建てまでの高層ビル等では第3次診断が必要になる場合が多く、診断費用だけで数千万円に及ぶケースもあります。
耐震診断の流れ
耐震診断は以下の流れで進みます。
- 予備調査:設計図書の有無、修繕履歴、被災履歴を確認、現地目視調査を経て、診断レベルを判断する。
- 現地調査:診断レベルに応じて必要な建物の部材寸法や配筋状況等の実測調査による既存図面との整合性確認、コンクリートコア採取による各種試験、建物傾斜測定、構造劣化状況等の調査を行う。
- 詳細診断:調査結果を基に耐震性を評価し、補強案や概算工事費を検討します。
建物の構造的特徴に応じた適切な診断レベル(診断次数)を設定することが重要です。 既存図が無い場合には、詳細な現地調査により耐震診断に必要な図面の復元を行います。
賢く使って費用を抑える!補助金制度
耐震診断や改修には高額な費用が伴うため、多くの自治体が補助制度を設けています。
政令指定都市を中心とした代表的な制度
| 地域(政令指定都市) | 耐震診断費用補助 | 耐震改修費用補助 | 特徴・上限額 |
|---|---|---|---|
| 東京都(23区) | 木造住宅で9割補助、上限10万円(区により異なる) | 工事費の1/2補助、最大150万円前後(区により異なる) | 公共施設や緊急輸送道路沿道建物は特例あり(区により異なる) |
| 大阪市(大阪府) | 診断費用の10/11補助、上限20万円 | 工事費の4/5以内、上限150万円 | 全国でも補助割合が高い |
| 名古屋市(愛知県) | 木造住宅は無料診断 | 工事費最大115万円、設計費20万円補助 | ブロック塀撤去支援も整備 |
| 横浜市(神奈川県) | 木造住宅は無料または低額診断 | 工事費最大120万円 | 中層マンションにも対象拡大 |
| 札幌市(北海道) | 木造住宅で費用の一部補助、上限10万円 | 工事費の2/3、最大100万円 | 積雪荷重を考慮した耐震化支援 |
| 福岡市(福岡県) | 木造住宅の精密診断を2/3補助 | 工事費の2/3、上限100万円 | 県と市の制度を併用可能 |
| 神戸市(兵庫県) | 診断費用の2/3補助、上限12万円 | 工事費の4/5、上限120万円 | 阪神淡路大震災後に強化された制度 |
| 京都市(京都府) | 木造住宅の診断を無料実施 | 工事費の1/2補助、上限120万円 | 歴史的建築物保存にも配慮 |
| 広島市(広島県) | 木造住宅の診断を無料または助成 | 工事費の2/3補助、上限100万円 | ブロック塀除却支援あり |
| 仙台市(宮城県) | 木造住宅で無料診断 | 工事費の1/2〜2/3補助、上限120万円 | 東日本大震災を踏まえた制度充実 |
自治体だけではなく、国(耐震対策緊急促進事業実施支援室)が申請・交付等を行う補助金もあります。
対象建築物の所在地で地方公共団体の補助制度が未整備の場合、国(耐震対策緊急促進事業実施支援室)が窓口となり、国が直接補助します。 一方で、地方公共団体の補助制度が整備されている場合は、当該自治体が窓口となり、国と自治体補助を併用する形となります。
建築物の区分により、補助金の対象となる行為が異なるため注意が必要です。詳細は以下をご参照ください。
<対象行為>
耐震診断:「平成27年度末までの措置」※最新運用は窓口で要確認
補強設計/耐震改修:いずれも補助対象
<対象行為>
耐震診断:国の直接補助なし(自治体へ要確認)
補強設計耐震改修:原則は自治体窓口(制度未整備なら国窓口)
<対象行為>
詳細診断/補強設計/改修工事:いずれも補助対象
<対象行為>
詳細診断:国の直接補助なし(自治体へ要確認)
補強設計・改修工事:原則は自治体窓口/未整備なら国窓口
<出典>耐震対策緊急促進事業実施支援室「窓口と補助対象」
https://www.taishin-shien.jp/hojyo/
補助金・助成金を利用する際の注意点
補助金・助成金を利用する際にはいくつかの注意点があります。 まず、最も重要なのは、耐震診断を始める前に必ず事前申請を行う必要があることです。 診断後に申請しても、補助金・助成金の対象にはなりません。 また、補助金・助成金の交付を受けるためには、第三者機関による「耐震判定委員会」の審査が必須となることが多いです。 さらに、建物の築年数、構造(木造・RC造など)、または用途(戸建住宅、マンションなど)によっては、制度の対象外となる場合があります。 特に、オフィスビルなど住宅以外の建築物を対象とした耐震診断や耐震改修に関する補助金制度は、住宅向けに比べると種類が少ないため、事前に条件をしっかり確認することが大切です。
補助金・助成金の申請手順(例)
- 事前相談:自治体の担当部署(建築指導課等)に確認。
- 助成金申請書の提出:診断・契約前に、自治体へ助成金申請必要書類を提出。
- 助成金交付決定:自治体から助成金交付決定書を受け取り。
- 建築士事務所との契約:登録耐震診断士や認定業者を選定。※建築士事務所等との契約は、助成金交付決定後に行うこと。
- 耐震診断の着手届の提出:耐震診断の着手届を自治体へ提出。
- 耐震診断の完了届の提出:耐震診断結果報告書等を自治体へ提出。
- 助成金の請求:助成金請求書及び支払金口座振替依頼書を自治体へ提出。
- 助成金の交付:自治体から指定口座へ助成金入金。
補助金・助成金の申請は必ず「診断前」に行う必要があり、手続きの不備や遅れがあると補助金・助成金を受けられない場合があります。 また、耐震診断を行う建築士事務所等との契約は、助成金交付決定の翌日以降とする必要があります。 交付決定前に契約してしまうと助成金対象外となってしまうので注意が必要です。
法律と耐震改修の義務化
既存不適格建築物すべてに耐震改修を義務化することは経済的に困難ですが、多くの人が利用する建物や、災害時に重要な役割を担う建物については、耐震診断・改修の義務または努力義務が課せられています。
「耐震改修促進法」で、耐震診断の義務付けの対象となる建物は以下の通りです。
①要緊急安全確認大規模建築物
不特定多数の方や、避難上特に配慮を要する方が利用する大規模建築物など
<参照>要緊急安全確認大規模建築物の規模要件等(東京都耐震ポータルサイトより)
https://www.taishin.metro.tokyo.lg.jp/pdf/tokyo/seismic_01.pdf
②要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)
特定緊急輸送道路の沿道の建築物で、高さがおおむね道路幅員の1/2以上のもの
<参照> 要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の要件等(東京都耐震ポータルサイトより)
https://www.taishin.metro.tokyo.lg.jp/proceed/topic03.html
「耐震改修促進法」に基づき、建物所有者は、耐震診断の義務や改修の努力義務、または診断・改修の努力義務を負います。 公共性の高い施設ほど責任は重く、社会全体の防災力を高めるための重要な取り組みと位置付けられています。
「義務」と「努力義務」の法的効力
「義務」 を怠る(不履行)と、違法 となります。その結果、行政処分・過料・罰則 などの罰則、契約における債務不履行 となり、損害賠償 や契約解除の対象となる等、法的措置がとられる可能性があります。
一方、「努力義務」 を怠っても、直ちに違法になったり、罰則の対象になることは少ないです。 しかし、全く問題がないわけではありません。 行政からの指導、勧告、公表の対象になったり、事故やトラブル発生時には、注意義務違反として過失の判断材料になる可能性があるため、注意が必要です。
法的効力という観点から見ると、「義務」は法的強制力があり、「努力義務」は法的強制力はないものの、無視できない責任を伴う、と理解するのが良いでしょう。
まとめ
耐震診断は、旧耐震基準建物の安全性を確認するために不可欠です。 費用は建物条件により数十万円から数千万円と幅広いですが、各自治体の補助金制度を賢く活用することで、大きな経済的負担を軽減できます。 また、特定の建物には法律上の耐震診断の義務付けがあるため、早めの対応が求められます。
リボビルには、構造設計に特化した専門家が在籍しており、中立的な立場から耐震診断を行います。 その後の補強設計、施工、そして建物の不動産価値向上まで、一貫したサポート体制を整えています。
建物の安全性と資産価値を将来にわたって守るため、「もしも」の不安を抱えたままにせず、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
耐震診断・耐震補強設計(非木造)なら全国対応可能!
まずはお気軽にご相談ください。